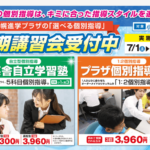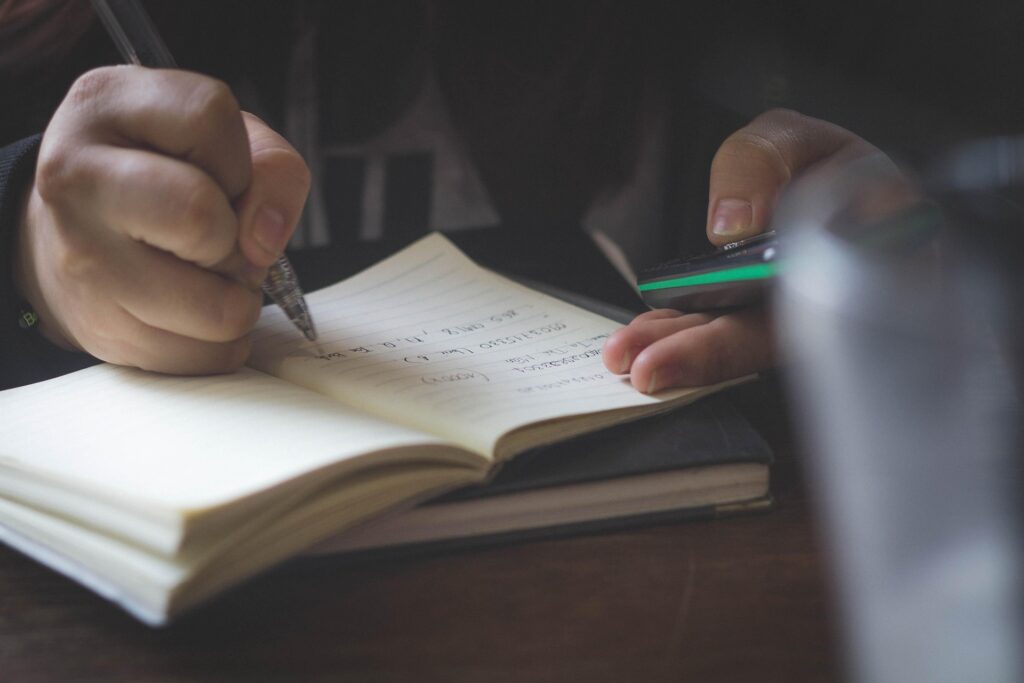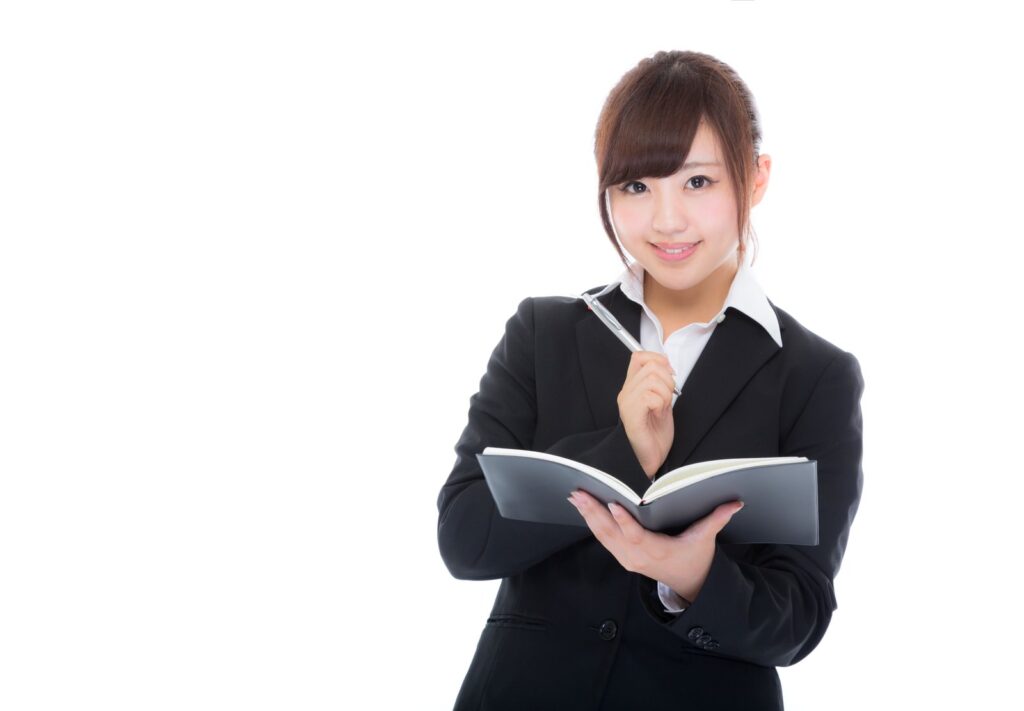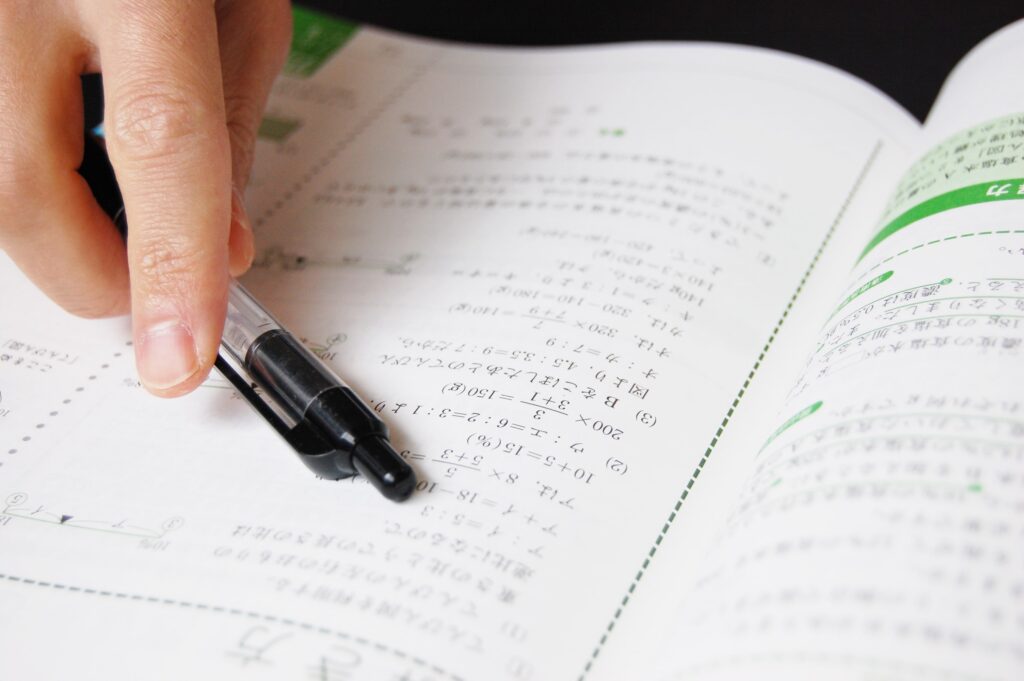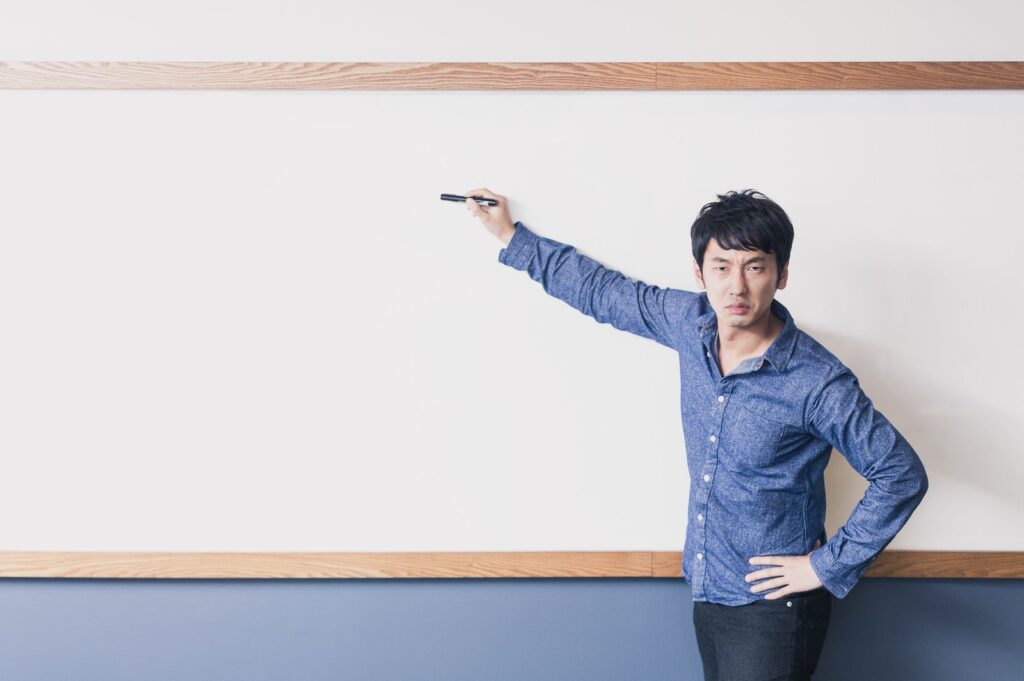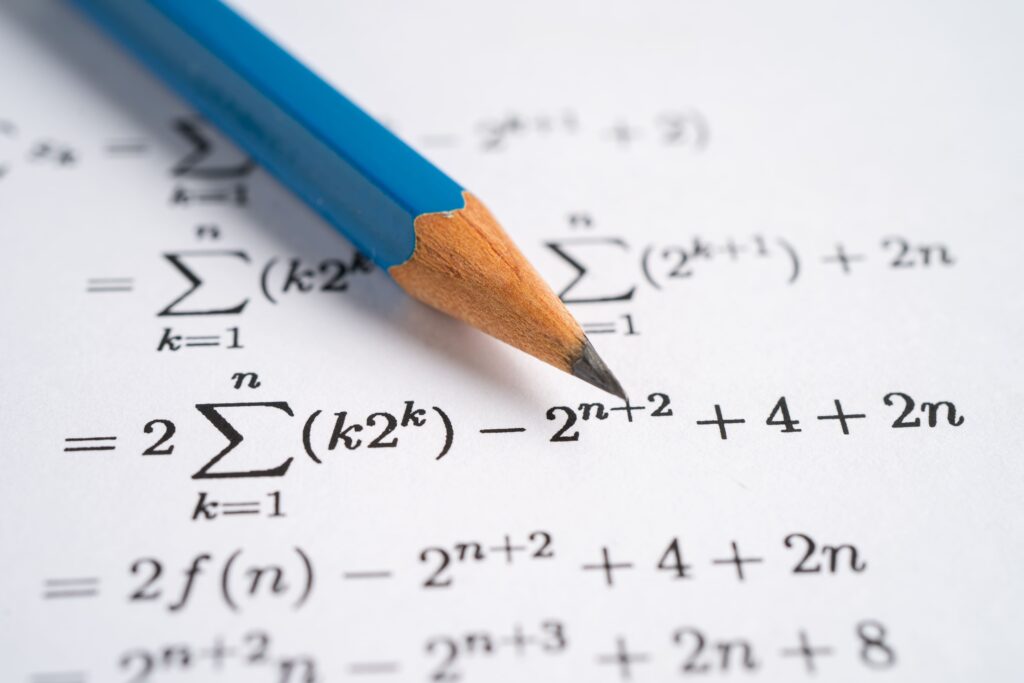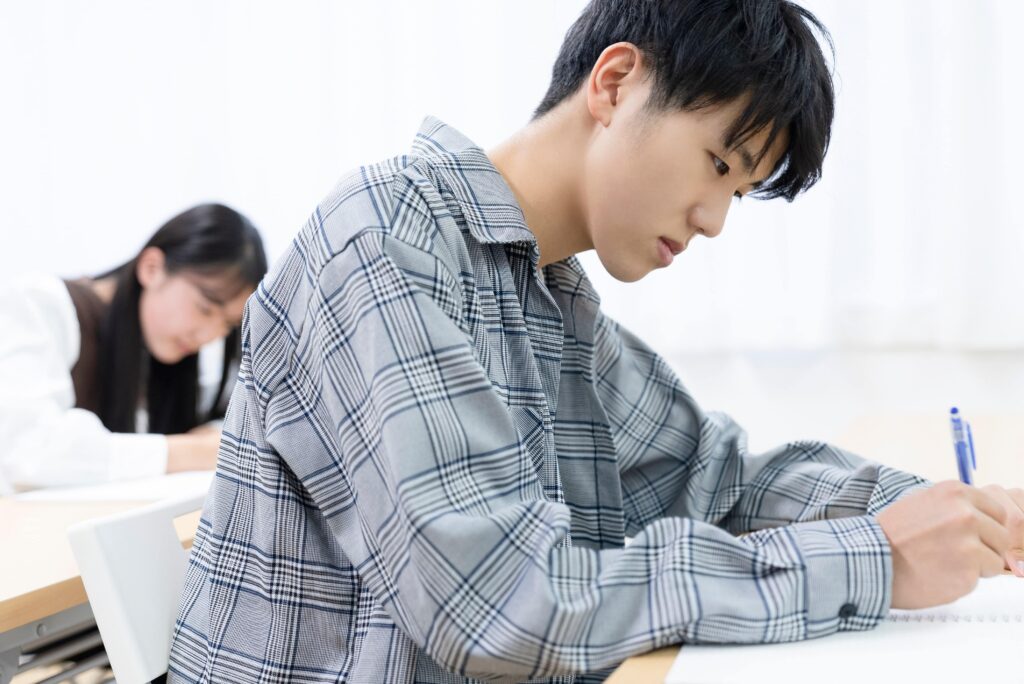【中学生向け】苦手教科の克服方法を解説
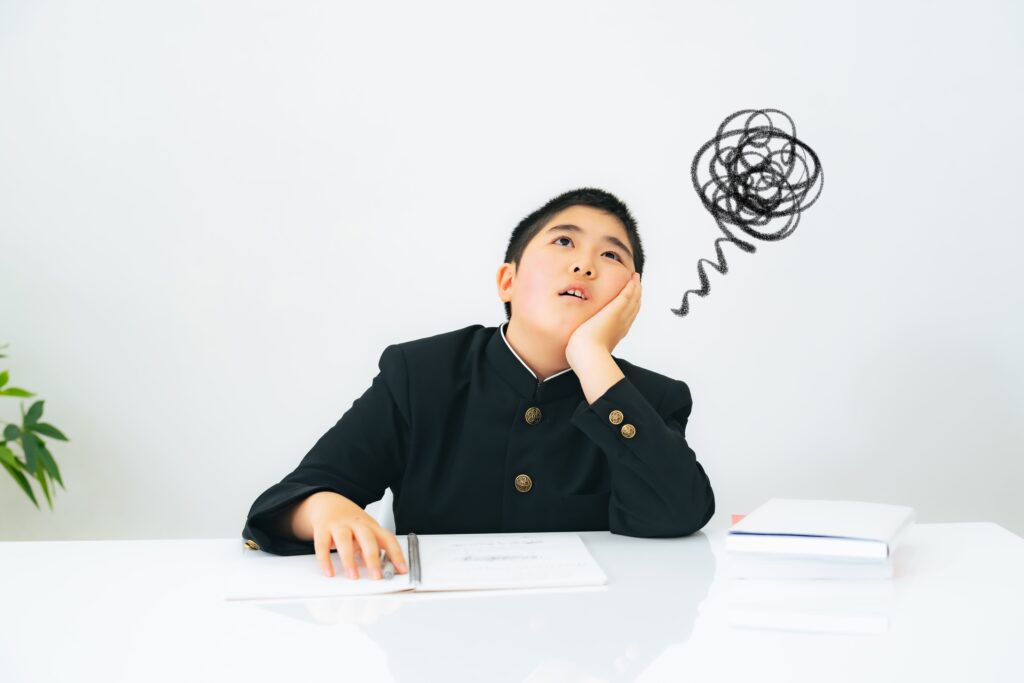
中学校に上がると、英語の授業が本格化したり、その他の科目の難易度もグッとあがります。そのため、苦手教科ができてしまう生徒も多いです。そこで本記事では、中学生に向けて、苦手教科の克服方法について徹底解説します。苦手教科がある子どもやその保護者の参考になれば幸いです。
なぜその教科が苦手なのか分析しよう
中学生にとって「苦手教科の克服」は重要なテーマです。しかし、そもそも何が苦手なのかを明確にできていないケースも少なくありません。はっきりと「この教科が苦手」と自覚している場合は比較的スムーズに対策を立てることができます。
しかし「なんとなく全部苦手」と感じている場合は、まずは自分の成績や学習の様子を振り返り、具体的にどの教科、またはどの分野に課題があるのかを特定する作業が欠かせません。
たとえば、通知表で他の教科が5段階評価の4であっても、数学だけが3であれば「自分は数学が苦手なのかもしれない」と気づくきっかけになります。このように、感覚だけでなく客観的なデータをもとに判断することが重要です。
さらに注意すべきは、得意だと感じている教科の中にも実は理解が浅かったり、苦手意識を持っていたりする細かな分野が潜んでいる可能性があるという点です。たとえば英語が得意と思っていても、実際にはリスニングが苦手であったり、文法の一部が理解できていなかったりすることもあります。
教科全体で見ず、単元や内容別に分解して分析することで、より具体的な対策が立てられるようになります。苦手教科を単に「嫌い」「わからない」で済ませてしまうのではなく「どの部分がどう苦手なのか」を言語化することが克服の第一歩となります。
原因を明確にすることで、必要な学習方法やサポートも見えてくるため、効率的かつ前向きに取り組めるようになります。
苦手を克服するための学習方法を教科別に紹介
中学生が苦手教科を克服するためには、自分に合った具体的な学習方法を見つけ、着実に実践していくことが重要です。ここでは、教科別に効果的な学習方法を紹介し、それぞれの特性に応じた対策のポイントを紹介します。
数学
数学に苦手意識を持つ中学生は非常に多いです。その大きな原因の一つは、小学校や前学年で学習した内容の理解が不十分なまま中学校の学習に入ってしまっている点にあります。
数学は積み重ねが重要な教科であるため、過去の内容があやふやなままだと、当然ながら現在の学習にもつまずきが生じます。このような場合には、苦手な単元をさかのぼって復習することが不可欠です。
「今さら小学校の内容に戻るのは…」と抵抗を感じるかもしれませんが、中学生になった今の視点で取り組めば案外スムーズに理解できることが多く、それほど時間もかかりません。
また、計算が遅い、あるいは間違いが多いことでテスト時間が足りなくなり、点数が伸び悩んでいる生徒も少なくありません。そうした場合は、まずは計算力の強化に集中し、反復練習でスピードと正確さを身につけることが求められます。
英語
次に、英語に苦手意識を持つ生徒の場合、学習に触れる機会そのものが不足しているケースが目立ちます。近年では、小学校でも英語教育が始まりました。
しかし、家庭での学習習慣がないまま中学校に入ってしまうと急に学習内容が難しくなり、ついていけなくなることがあります。まずは英語を身近な存在として捉え、生活の中に自然に取り入れる工夫が大切です。
例えば、YouTubeやTikTokなどの英語コンテンツを字幕なしで聞いてみる、洋楽に触れてみる、海外のニュースを簡単にチェックしてみるなど、興味のあるものから始めてみることをおすすめします。英語への抵抗感が和らぎ、やる気の向上にもつながります。
文法や単語をただ暗記するのではなく「使う場面」をイメージすることで、実践的な理解を深めていくことができます。
国語
国語が苦手な中学生の多くは、読書に対する苦手意識を持っていることが一因です。この場合、無理に難しい本を読む必要はなく、漫画や絵本など読みやすいものから始めて、文章に触れる習慣を作ることが大切です。
一方で、読書は好きなのに国語の点数が伸びない生徒もいます。これは、国語の問題に対して「自分なりの答え」を書いてしまい、設問の意図に沿わない回答になっているケースです。
国語のテストでは「文中から根拠を探す」ことが求められるため、問題文をよく読み、答えのヒントがどこにあるのかを的確に探し出す練習が必要になります。
また、漢字の習得は国語力の基本中の基本です。小学校で習った漢字を含め、日常的に書いて覚える時間を確保することが、語彙力や読解力の底上げにもつながります。
社会・理科
最後に、社会や理科は他の教科に比べて扱う内容が多岐にわたっており、単元によって難易度や理解度が大きく異なるのが特徴です。社会であれば地理・歴史・公民、理科であれば物理・化学・生物といったように、ひとくくりにするのではなく、細かく分けて分析する必要があります。
これらの教科では「どの分野が苦手なのか」を明確にすることが第一歩です。そして、その分野において必要な前提知識がどこにあるのかを探り、さかのぼって学習を進めましょう。
例えば、理科の化学分野が苦手であれば、物質の性質や化学式の基本から復習し、理解を深めていくことが重要です。社会も同様で、歴史が苦手な場合は時代の流れや重要な出来事の背景をざっくりと押さえることで、暗記に頼らず理解を進められます。
まとめ
中学生にとって、苦手教科の克服は学力向上の大きなカギとなります。本記事では、まず「なぜ苦手なのか」を分析し、感覚に頼らず成績や学習内容を振り返ることの重要性を紹介しました。その上で、教科ごとの特徴に合わせた具体的な学習方法を提案しています。数学は基礎の見直しと計算力の強化、英語は日常的な接触と実用的な理解、国語は読解力と漢字の習得、社会・理科は分野ごとの弱点把握とさかのぼり学習がポイントです。「苦手」の正体を明らかにし、適切な方法で取り組むことで、着実に学力を伸ばすことができるでしょう。
を意識した札幌でおすすめの学習塾は…
-
 引用元:https://www.asuxcreate.co.jp/pg4263125.html
引用元:https://www.asuxcreate.co.jp/pg4263125.html
戦略個別のNEXT(ネクスト)は、「自分たちの子どもに受けさせたい教育」をモットーに、自分たちが使いたいサービスやプランを吟味して納得したものを提供しています。そのため保護者の方の目線に立ったサポートが手厚く、子供の学びの様子がInstagramで発信されていたり、透明性の高い裏側まで自信を持てる運営体制が魅力です。また安心・納得して任せてもらえる”自信”があるのでご入会から30日以内であれば、受講料を全額返金してくれます。ぜひ一度HPをご覧ください。